「多様性」は社会として大切にすべきもの。企業としても「多様性」への配慮を絶対に忘れてはいけない──そんな意識の高まりから、いまや多くの企業が社会的責任として強く意識しつつ、「多様性」に取り組むようになっている。いわゆるダイバーシティ推進だけでなく、近年ではマーケティング領域においても、広告やキャンペーンなどに多様性を反映するインクルーシブマーケティングが当然の取り組みになりつつある。
しかし、広く世界を見まわしてみると、こうした取り組みは、多くの生活者から歓迎される一方で、既存顧客の購買意欲の低下やブランド離れにつながることもあるという。
なぜ社会的に意義があるはずの「多様性」への取り組みが、ときに支持を失うのか――。
この現象について、バーミンガム大学ビジネススクールの准教授Louiseらは、論文『彼らは私の仲間ではない:インクルーシブ・マーケティングが裏目に出たとき1』で、顧客心理の観点から分析している。
背景にあるのは「こう見られたくない」という心理
企業が顧客がもつ多様な背景を理解し、彼らを包摂できるようにサービス提供したり、採用するなどの戦略的な取り組みのことを「顧客の多様性への取り組み (Customer Diversity Initiatives; CDI)」という。一般的には、CDIは顧客のロイヤリティを高め、市場の裾野を広げるとされており、広告やキャンペーンに多様な人種、年齢、性別、性的指向、身体的特徴を持つモデルを起用するといったインクルーシブ・マーケティングもここに含まれる。
しかし、CDIを実践すれば、好意的に受け止められるのかといえば、現実はそう単純ではないようだ。
米国のビールブランド「Bud Light」は、2023年にトランスジェンダーのインフルエンサー Dylan Mulvaney とのコラボレーションを行った後、SNS での保守層の反発が激化。米国内での販売量は約10~15%減少し2 3、利益も大幅に落ち込む事態に直面した。また、米小売大手「Target」は、LGBTQ+の権利を啓発するプライド月間に関連商品を展開したところ、一部顧客から反発を受け、売り上げが5%落ち込んだという。こうした事例は、「多様性の推進が、ときにブランドの支持を揺るがす」という現実を浮き彫りにしている。
背景にあるのは、生活者自身が「自分はこう見られたくない」「一緒にされたくない」と感じる「解離的集団 (距離を置きたいと感じる集団)」への意識である。そもそも人はブランドを自己イメージの延長として選ぶ。そのため選ぼうとしているブランドが、自分が距離を置きたいと感じている集団と結びつくと、「自分もその一員と思われるのではないか」という強い不安、すなわち「アイデンティティを損なう脅威」を感じるのだという。
Bud Lightのケースでは、多様性を訴求したことで、販売量が10〜15%も減少するという大きな影響が起こったわけだが、その理由は「一部の顧客がアイデンティティの面で心理的不安を抱き、自己イメージを守るためにブランドから離れた」ことにある、とLouiseらは説明する。
キャンペーンの“継続期間”がブランド離れを左右する
Louiseらは、「多様性への取り組み」がブランド離れを招くメカニズムを検証するために、生活者が心理的に「距離を置きたいと感じる集団」をブランドが支援した場合に、顧客に起こる購買意欲の変化について、会議室と実際のフィールド広告の両方で実験を行った。その際、彼らはキャンペーンの期間に注目し、つぎの2つの条件それぞれについて実施・分析している。
- 一時的な取り組み:特定の記念日やイベントに合わせて実施される1ヶ月限定
- 継続的な取り組み:期間を定めず、永続的なパートナーシップ
会議室での実験では、被験者に「お気に入りのカフェが、自分が距離を置きたいと感じる集団を支援する」というシナリオを提示。その取り組みが「一時的」な場合と「継続的」である場合の両方について調査したところ、、取り組みが「一時的」であれば、購入意欲はある程度維持された。が、「継続的」である場合は、購買意欲は大きく減少した。
同じ傾向は、Facebook広告を用いたフィールド実験でも確認された。「距離を置きたいと感じる集団」への「継続的」な支援を打ち出した広告よりも、「一回限り」の支援を打ち出した広告の方がクリック率が約2倍高く(0.67% vs. 0.36%)、継続的な取り組みの方がブランド離れにつながりやすいことが実証された。
本来であれば、社会的意義があるはずの「多様性に配慮したマーケティング」も、「距離を置きたいと感じる集団」が対象となり、かつその訴求が継続的なものである場合は、既存顧客を遠ざけてしまうリスクがあるということだ。つまり、「多様性への取り組み」はブランド価値を高めるばかりではなく、顧客のアイデンティティをネガティブに刺激し、ブランド離れを招く可能性があるというのだ。
共感か、損得か。顧客タイプによっても反応は変わる。
ただし、すべての顧客がまったく同じように反発するわけではない。Louiseらは、顧客とブランドの関係性のあり方によって、反発の仕方が異なることも明らかにしている。先に取り上げたキャンペーンの期間の長さが顧客に与える影響にしても、その顧客がブランドとどのような関係を築いているかによって、全く逆の効果を生むこともあるという。
Louiseらは、ブランドとの関係性に応じて、被験者を次の2種類に分類した実験も行っている。
- 共感重視の顧客 (Communal Customers)
ブランドとの間に、感情的なつながりやコミュニティとしての一体感を求めている。ブランドの姿勢やストーリーに共感しており、製品やサービスを使うことで精神的な満足感を得る。 - 損得で選ぶ顧客 (Exchange Customers)
ブランドとの関係を実利的・合理的に捉え、コストパフォーマンスや得られるメリットを重視している。ポイント、割引、価格など、自分にとってどれだけ「お得」か、「価値があるか」を基準にブランドを選ぶ。
そのうえで、架空のブランドが自分が「距離を置きたいと感じる集団」を支援するキャンペーンを行うというシナリオを提示し、それが一時的な取り組みである場合と、継続的な取り組みである場合とで、評価がどのように変わるかを検証した。
その結果、両者の反応は対照的だった。「共感重視の顧客」が強く反発を示したのは「一時的な取り組み」に対してだった(図1 左側、黒塗り棒グラフ、平均 2.56)。彼らにとっては、短期間だけの関与は誠実さに欠けるものと映り、むしろ裏切られたような感覚を抱くのである。
一方で、「損得で選ぶ顧客」は「継続的な取り組み」に対して強く離反の意思を示した(図1 右側、斜線棒グラフ、平均 2.46)。自分が「距離を置きたいと感じる集団」との結びつきが恒常化されることを嫌い、それがブランドから離れる動機となる。
マーケティング施策を行う企業の目線で見れば、「共感重視の顧客」には「一次的な関与」がリスクとなり、「損得で選ぶ顧客」には「継続的な関与」がリスクとなる。顧客のブランドとの関係性タイプにより、「多様性の訴求」のキャンペーンがもたらす効果は真逆になりうるのである。

Repatronage reduction: 再購入意欲の減少、ブランド離れ
Episodic CDI: 一時的な多様性への取り組み、Ongoing CDI: 継続的な多様性への取り組み
Communal(黒塗り): 共感重視の顧客、Exchange(斜線): 損得で選ぶ顧客
別の言い方をすれば、多様性への取り組みは、ある顧客には「親しさの欠如」と見なされ、別の顧客には「過剰な関連付け」と映る──この実験結果は、マーケティングにおける「顧客との関係性の視点」の重要性を示唆している。ここにある顧客心理を理解しなければ、思わぬブランド離れを招くリスクがあるのだ。
反発をやわらげるカギは「隙間」──ブランドが取るべき多様性訴求の戦略
では、ブランドや企業は、どうすれば顧客の反発を避けつつ、「多様性」という社会的責任を果たすことができるのか。論文の最後でLouiseらは、その鍵が「顧客のアイデンティティを脅かす感覚をどう和らげるか」にあると指摘している。Louiseらは、過去の実験で最も反発が強かったシナリオ(「共感重視」顧客×「一時的」取り組み、「損得で選ぶ」顧客×「継続的」取り組み)をあえて再現し、その反発を抑える方策として、次の3つの戦略について検証している。
- サブブランド戦略: 多様性への取り組みを、親ブランドとは別の新しいブランドで行う
- カスタマイズ戦略: 顧客が商品やデザインを自分の好みにあわせて選べるようにする
- 包括性戦略: 「特定の集団のため」ではなく「すべての人のために」とメッセージを広げる
このうち、顕著に効果があったのは、「サブブランド戦略」と「カスタマイズ戦略」である。
「サブブランド戦略」をとれば、親ブランドは「(顧客が)距離を置きたいと感じる集団」と直接結びつくイメージを避けることができる。顧客は心理的な距離を保つことができるため、アイデンティティを脅かされる感覚を和らげることが可能となる。
「カスタマイズ戦略」は、顧客が商品に自分らしさを付け加えることができる「自己表現の余白」をもたらす。これにより、ブランドが発信する特定の価値観に自分が従属させられているという感覚を緩和でき、「自分の選択でこのブランドの商品を使っている」という意味付けが可能になる。
共通するポイントは「隙間」である。「サブブランド戦略」は「距離を取る余地」、「カスタマイズ戦略」は「自己表現の余白」と、いずれも顧客に「隙間」を与えている。この「隙間」が緩衝材となり、ブランド観と顧客の価値観との衝突をやわらげ、ブランド離れのリスクを大きく減らすのである。
一方で、「包括性戦略」の効果は限定的だった。「損得で選ぶ」顧客には一定の効果が見られたが、「共感重視」の顧客には文字どおり響かなかった。彼らがブランドに求めている「誠実さ」に対して、「みんなのため」というメッセージは大雑把で具体性がなく、適していない、と論文は指摘している。
*
大切なのは、「インクルーシブ施策にエクスクルーシブ要素を併せる」 という発想だ。つまり、正しいメッセージを掲げるとはいえ、誰もがそこに同じ形で巻き込まれる必要はない。心理的な距離を選べる仕組み(サブブランド戦略)や、自分らしさを上書きできる仕組み(カスタマイズ戦略)といった選択肢や逃げ道を用意することで、顧客のアイデンティティを損なう脅威を減らし、反発を抑制することができる。
取り組み自体の是非を問うのではなく「誰にどう伝え、どう関わってほしいか」を明確にしつつ、関与のレベルを調整・選択できる「隙間」を作る。ここにこそ、多様性施策と、ブランドの持続的な成長を両立させる鍵がある。
参考文献
- Hassan, L.M., McGowan, M. & Shiu, E. They’re not my people: When inclusive marketing backfires. J. of the Acad. Mark. Sci. 53, 563–587 (2025). https://doi.org/10.1007/s11747-025-01105-5
クリエイティブコモンズ CC BY 4.0のもとライセンスされている参考文献を改変しています。 ↩︎ - Mary Roeloffs, Forbes Staff. “Bud Light Sales Down 10% After Right-Wing Boycott Over Campaign With Transgender Influencer“. Forbes. 3 August 2023. (2025年9月1日 閲覧) ↩︎
- Sarah Taaffe-Maguire. “Dylan Mulvaney: Bud Light beer takes sales hit after backlash over ad campaign featuring transgender influencer“. Sky News. 2 August 2023. (2025年9月1日 閲覧) ↩︎









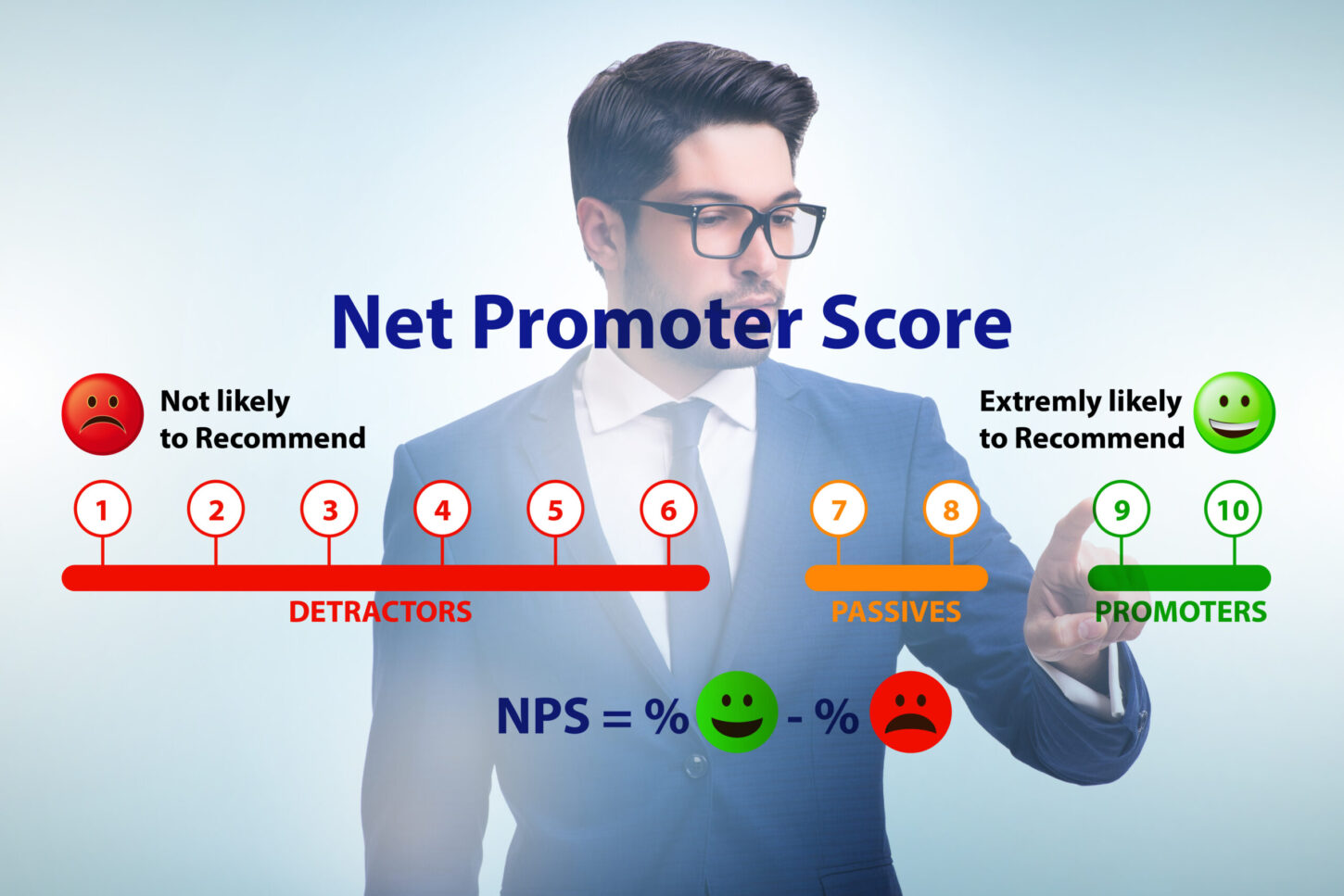










コメント